保育士さんと保護者さまを繋ぐ連絡帳。連絡帳は保護者様とのコミュニケーションとして重要なツールですが、それゆえ些細な事で保護者様の誤解を招くような事態は避けたいもの
ただ「連絡帳を書くのがツライ」「連絡帳を書くのが苦手」という層が一定数いらっしゃいます。
毎日、連絡帳を書くのは保育士さんにとって大変ですよね・・・
しかし連絡帳の書き方を抑えてしまえば難しく考えずともスラスラ欠けてしまえるものです
ということで今回は【保育園での連絡帳・連絡ノートの書き方まとめ!例文とコツは??】についてまとめましたので参考にしてみてください!!
ページコンテンツ
保育園の連絡帳ってなんで必要なの??

まず、保育園の連絡帳について知っておきましょう。
(社会福祉法人)日本保育協会の「保育所保母業務の効率化に関する調査研究」によると、連絡帳のねらいとは
“1日の大半を保育園で過ごす子どもの様子を保護者に伝えたり、また、家庭での様子を知らせ合うノート”
とのこと。
保護者に子どもたちの保育園での様子やあった事を伝えて、家庭での出来事や体調など知らせておきたい事などを保育園に伝えるためのノートで保護者と保育士を繋ぐとても大切なものです。
連絡帳の内容は??
基本は体調など健康面はしっかりと記録するように!
・咳や鼻水が出ていたとき
・食欲がなく、給食を残したとき
・午睡が少なかったとき
・いつもより元気がなかったとき
・便がゆるかったとき
・体温がいつもより高かったとき
といった「園児の健康に関すること」に加えて、フリースペースにその日あったこと、例えば「公園まで散歩に行って氷鬼をした」といったことを書くのが基本です。
いつもと違う姿が見られたときには、必ず伝えて家庭でも様子をみてもらうようにしましょう
また体調以外にも、子どもが新しくできるようになったことを書くのもいいでしょう。
例えば砂遊びをした…という同じ出来事でも、作るものも、お友達との関わり方も異なります。楽しそうに○○君とはしゃいでいた。スコップを○○ちゃんに貸してもらってありがとうとお礼が言えた、そんな小さなエピソードでも様子が伝わりやすくなります。
伝わりやすい連絡帳の書き方!
基本的な書き方をご紹介します。
・基本の【5W1H】
- When いつ
- Who だれが
- Where どこで
- What なにを
- Why なぜ
- How どのように
この5W1Hを念頭に置いて書くと、相手に伝わりやすい文章が書けると言われています。
例えば「○○くんが紙飛行機で遊びました」よりも、「○○くんと□□ちゃんが延長保育の時間に紙飛行機を作ってどっちが良く飛ぶか競争しました」と書いた方が、園児の状況が良く分かります。
事実を書くだけではネガティブになることも、切り口や書き方を変えればポジティブに、受け入れやすく伝えることができます。不安を与える要素は避け、対応を一緒に考える姿勢を伝えて行きましょう。
連絡帳のネタ・例文
・「知りたいこと」を簡潔に!
とにかくたくさん書こうとすると先生方も負担に感じてしまうでしょう。負担をなくすために、年齢別に「保護者の方々はどのようなことが知りたいのか?」を抑えたうえで、今日の出来事を簡潔に伝えられると良いですね。
園での様子を伝えるケース
今日は、クラスみんなで鬼ごっこをしました。
最初は、「やらない」と言って見ている姿がありましたが、お友だちが走っている姿を見て、
「やっぱりやる!」と入ってきて思いっきり走り、鬼ごっこを楽しみました。
初めは「やりたくない」とマイナスな姿も書いていますが、友だちの姿に刺激をもらっていっしょに遊べたことを書くと現実的で、
最終的にいっしょになって楽しめたと保護者の方は安心するでしょう。
喧嘩など、トラブルを伝えるケース
今日、電車のおもちゃで遊んでいるときに、「青色の電車が使いたい」とお友だちと電車の取り合いになりました。
どうしたら良いかを考えるように声をかけると「貸してって言う」と自分で考え、
お友だちにきちんと伝えて電車で遊ぶことができました。
取り合いになった事実を伝えた上で、子ども自身がどうしたら良いかを考えて行動できたと結果を伝えましょう。
■保護者の方を褒める
仕事をして、子育てをして…くたくたな保護者の方も多いでしょう。
「いつもご苦労様です!」「お母さん本当にすごいですね!」「尊敬します!」そう一言伝えることで「先生以外誰も言ってくれないから嬉しいです!」なんて返してくれました。褒められることでお母さんも笑顔になり、私もその姿を想像すると微笑ましくもなります☆
■子どもの”できた”を褒めるケース

「今日初めて○○を食べることが出来ました!」
「上手にたっちが出来ました」
「お友達におもちゃを貸してあげる姿がありました。優しいですね」
など、日々の成長の記録がわかるように書いています。
園での様子は家庭と違う!と話す保護者方も多くありません。
そのためどんな小さなことでもその子の様子を書いています。
そうすることで、「家では○○することを嫌がるので、教えてもらった方法で家でもやってみます!」「お友達と遊ぶ姿があり嬉しいです。」などと、会話が弾みますよ☆
連絡帳の注意点
続いては、連絡帳を書く際に気を付ける点、注意したいポイントをご紹介します。
・丁寧な字で書く
もちろん達筆なら言うことありませんが、字が下手でも気に病むことはありません。たとえ下手でも丁寧に書くことが大事です。
・言葉遣い
保護者とは節度を持った付き合い方が必要ですし、連絡帳も言葉遣いは丁寧にしましょう。
ある相談サイトで「子どもに~してあげた」と連絡帳に書いてあったのがおかしくないですか?と保護者が質問していました。
これに対して、賛否両論の回答でしたがやはり受け取り方の違いかも知れませんね。読む保護者の気持ちになって言葉遣いを選べるといいですね。
・トラブルの際は口頭でも伝える
連絡帳は連絡事項がメインですから、園児がケガをした、お友達とケンカをしたといったトラブルを、連絡帳での記述だけで済ませてしまうのはあまりおすすめできません。
その日あったトラブルは、お迎えの時間に直接保護者に口頭で伝えましょう。
直接聞かされれば納得できるものも、ただ連絡帳で事務的に知らせられたらこじれてしまうかも知れません。
まとめ
保育施設によっては卒園時、書きためた連絡帳を保護者に手渡すところもあるようです。「少し歩くそぶりを見せました」「お友だちと遊んでいて、おもちゃを貸してあげていた」そんな日常の出来事は、保護者にとってはもちろん、大きくなった子どもたちにとっても、大切な思い出として、残ってゆくことでしょう。
…だからこそ、記入の際には「明るくあたたかい文章で書く」「様子が思い浮かぶように書く」「長所など出来るだけポジティブなことを書く」などの工夫が必要です。
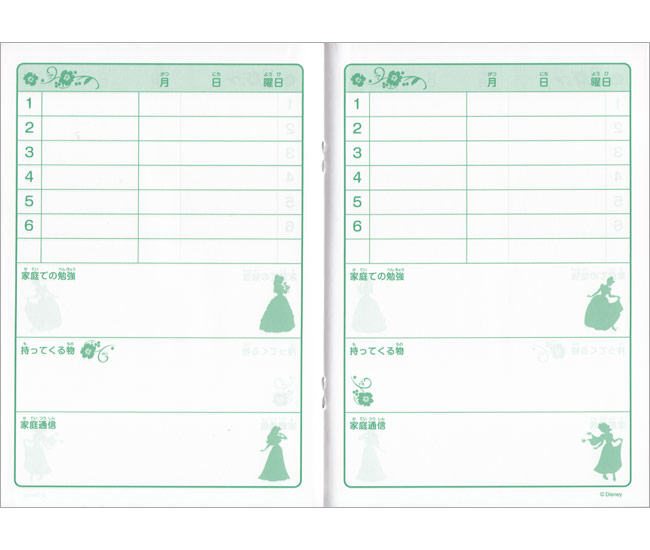

コメントを残す